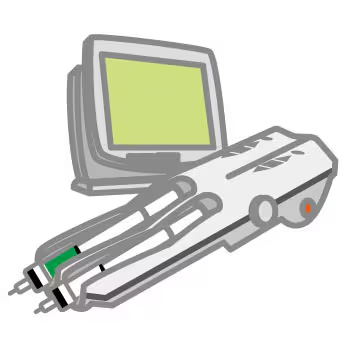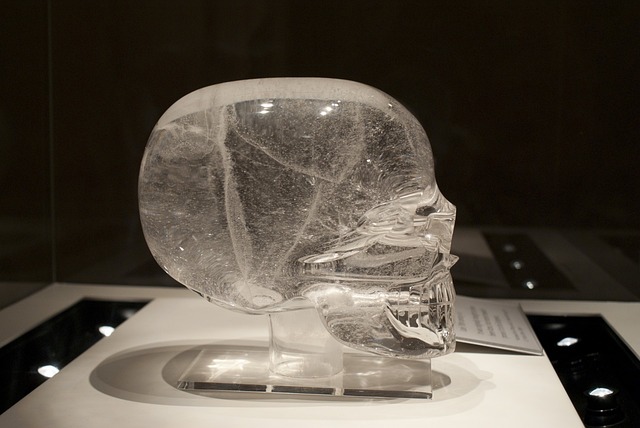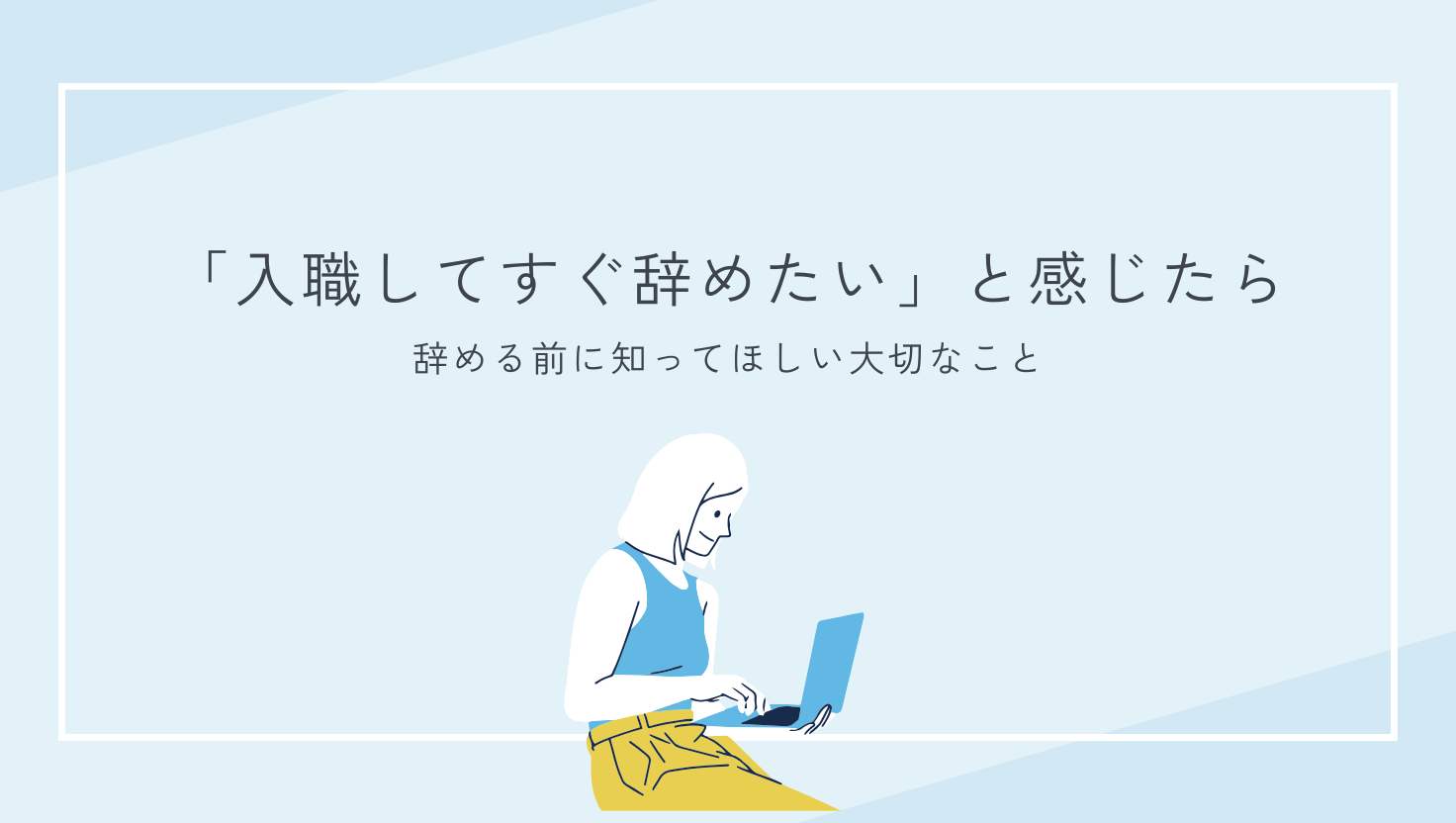放射線技師のサービス残業とプライベート:どうすればサービス残業じゃないと認めてもらえる?

サービス残業と向き合う放射線技師

チーム医療の柱として欠かせない放射線技師。
私たち放射線技師が抱える課題の一つに、サービス残業があります。
この記事では、放射線技師が直面するサービス残業とプライベートの調和の難しさに焦点を当て、健康的な働き方を実現するためのアプローチについて探っていきます。
- サービス残業が発生する具体的な事例
- サービス残業に対する解決策
きんちゃんの実体験に基づく話も含めていますので、同じ境遇の方もいるかもしれませんね。
サービス残業がプライベートの邪魔をする
放射線技師は患者の健康診断に欠かせない仕事を担当していますが、その一方でサービス残業が日常茶飯事となり、仕事とプライベートのバランスが難しくなっています。

この課題が放射線技師たちに与える影響や、プライベートの充実度が減少する悩みを共有し、解決への一歩を踏み出しましょう。
残業とサービス残業は分けて考えます
前提の確認もしておきましょう。
この記事におけるサービス残業の定義は以下の通りです。
サービス残業:業務時間を超えて業務を行っているにもかかわらず、賃金が発生しないこと
そのため、
- 緊急の検査や手術で定時を過ぎてしまった。
- 業務を残って行えないか?の事前連絡を受けて残業をした。
などのケースは、残業代が発生する以上、例外とします。
もっとも、上記ケースでも残業代が発生しないのであれば、早々に今の職場に見切りをつけるのが良いでしょう。

あなたを必要としているより良い職場は、他にもたくさんあるので。
サービス残業が発生するケースと解決策5選
本題に入ります。
ここからは、サービス残業が発生するケースと解決策5選を順番に紹介してきますね。
とはいっても、サービス残業が発生するケースはこれだけなのではないでしょうか?
勉強、自己研鑽として扱われる。
勉強、自己研鑽として扱われる。

きんちゃんも経験したケースです。
新人、ベテランに限らない話ですが、誰もが一度は身に覚えがあるのではないでしょうか?
特に、最初の数か月や始めてやる検査、機械操作の準備、練習でサービス残業をすることはあります。
その理由と上司の思考をまとめてみました。
業務への不慣れさ

新人はまだ業務に不慣れであり、そのため仕事の効率が低く、思うように成果が出せない可能性があります。
他の先輩技師たちに早く追いつけるように人一倍努力する必要があることから、自己研鑽という名のサービス残業を暗に命じられることがあるようです。
<上司の思考>
上司は日々の業務において効率と即戦力を重視しているため、未熟なスタッフに時間をかけて教えることを「非効率」と感じている可能性があります。
そのため、「自分で覚えてから来てほしい」といった態度を取ることもあるでしょう。
予算や人員の制約

組織や部署の運営には限られた予算や人員があり、教育や指導に時間を割く余裕がないケースがあります。
新人がミスをした際のフォロー体制も限られており、結果的に他のスタッフへの負担が増えることが懸念されます。
誰かの尻ぬぐいで、やむを得ず短時間のサービス残業をしたことがある方も意外といることでしょう。
<上司の思考>
経済的な制約や人的リソースの最適な配分を考える中で、「今は新人を丁寧に育てる余裕がない」と感じている可能性があります。
業務を回すことが最優先となり、新人教育が後回しになってしまうこともあるでしょう。
成果が見込みにくい学習

新人が取り組もうとしている学習活動が、目の前の業務に直接結びつかない場合、上司からの理解が得られにくくなります。
たとえば、長期的なスキルアップや知識の習得であっても、それがすぐに成果として現れないと、「意味がない」と捉えられてしまうかもしれません。
新人の場合、最初の目標は「一人で業務を回せるようになること」ですから、それに繋がらないことをされたら「意味がないことをしている」と判断されてしまいかねませんね、、、
<上司の思考>
上司は、「今やるべきことは業務で成果を出すこと」だと考えており、短期的な業務貢献につながらない活動には時間を割いてほしくないと感じている可能性があります。
その結果、学習の優先度が下がり、指導や支援が受けにくくなることがあります。
一つ一つ冷静かつ論理的に考えれば、納得できないものではありませんね。

では、どうすれば良いのでしょうか?
解決策はこれだ!

サービス残業を、れっきとした残業と認めてもらうための解決策をきんちゃんは以下のように提案します。
一つずつ詳しく説明しますね。
透明性とコミュニケーション

まずは上司とのコミュニケーションを強化し、自身の学習の進捗や成果について透明性を持たせることが重要です。
学んだ内容が業務にどれだけ貢献するかを具体的に伝えましょう。
何をやっているか分からないことに時間を使われることを嫌う上司の考えを利用して、自分の作業に正当性があることを認めてもらうということです。
円滑にコミュニケーションを進めるためにも日ごろからの会話を積極的に行っていきましょう。
成果の可視化
学習活動がもたらす具体的な成果を可視化し、業務の効率向上やチームの発展にどのように寄与するかを上司に示すことが大切です。
成果を具体的な数字や事例で示すと説得力が増します。

要するに、自分の勉強した内容が如何に業務に貢献しているかを示すのが大事だということですね。
優先順位の共有
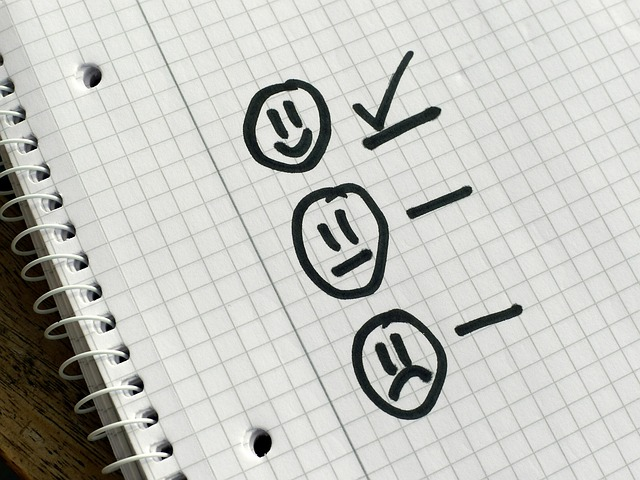
学習活動と業務の優先順位を上司と共有し合い、どちらも両立させるための柔軟な働き方やスケジュールの提案を行いましょう。
タスクの優先順位を明確にし、必要ならば調整を図ります。
スケジュール管理をして業務時間内に余裕をもって仕事を終わらせられれば、他のことをやる時間が生まれるということですね。
やらなくてもよいことに時間を割かずに、最優先でやること(新人なら、一つでも多くの検査のやり方を覚える、など)に全力を注ぐということです。
チームワークの意識

学習活動を通じて得たスキルや知識が、チーム全体に与える影響を共有し、他のメンバーとの協力や情報共有が効果的であることを示すことが有益です。
他のメンバーも利益を得られるような形にすることが大切です。
自分一人だけが利益を享受しては、私利私欲のものとみなされてしまいます。
気を付けましょう!
柔軟な働き方の提案
柔軟な働き方を提案し、必要な業務は適切にこなしつつ、残業を最小限にする方法を検討します。
リモートワークやフレキシブルな労働スケジュールの導入を検討してみましょう。

早出や遅出で残業をする前に、他の人に業務を引き継ぐ形が代表的な例ですね。
始業点検や就業点検など、病院によってルールが異なるのでいろいろな話を聞いてみると違いにびっくりしますよ!
まとめ

いかがでしたか?
結局のところ、上司には上司なりの考え方があります。
それを真っ向から否定してこちらの言い分だけを押し通すといった力業では、議論は平行線のままでしょう。
自らの行いが業務にいかに有用化を伝えるために、冷静かつ建設的なコミュニケーションを心がけ、上司との信頼関係を築くことが重要です。
この記事の内容が、新人が今の作業をれっきとした残業として認めてもらう上で役立つことを願っています。
悩みを先輩に共有して、手助けしてもらうのも有効かもしれませんね。
ではまた