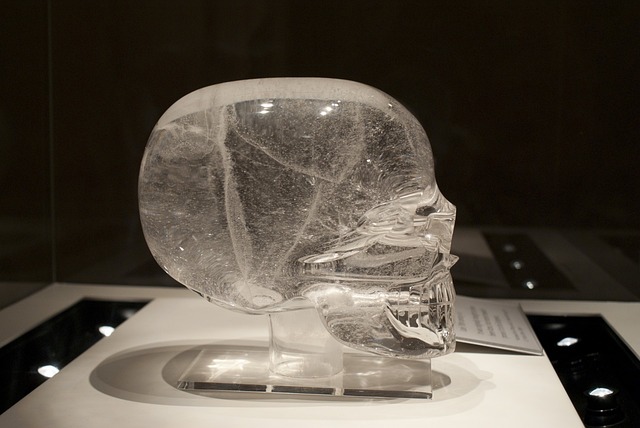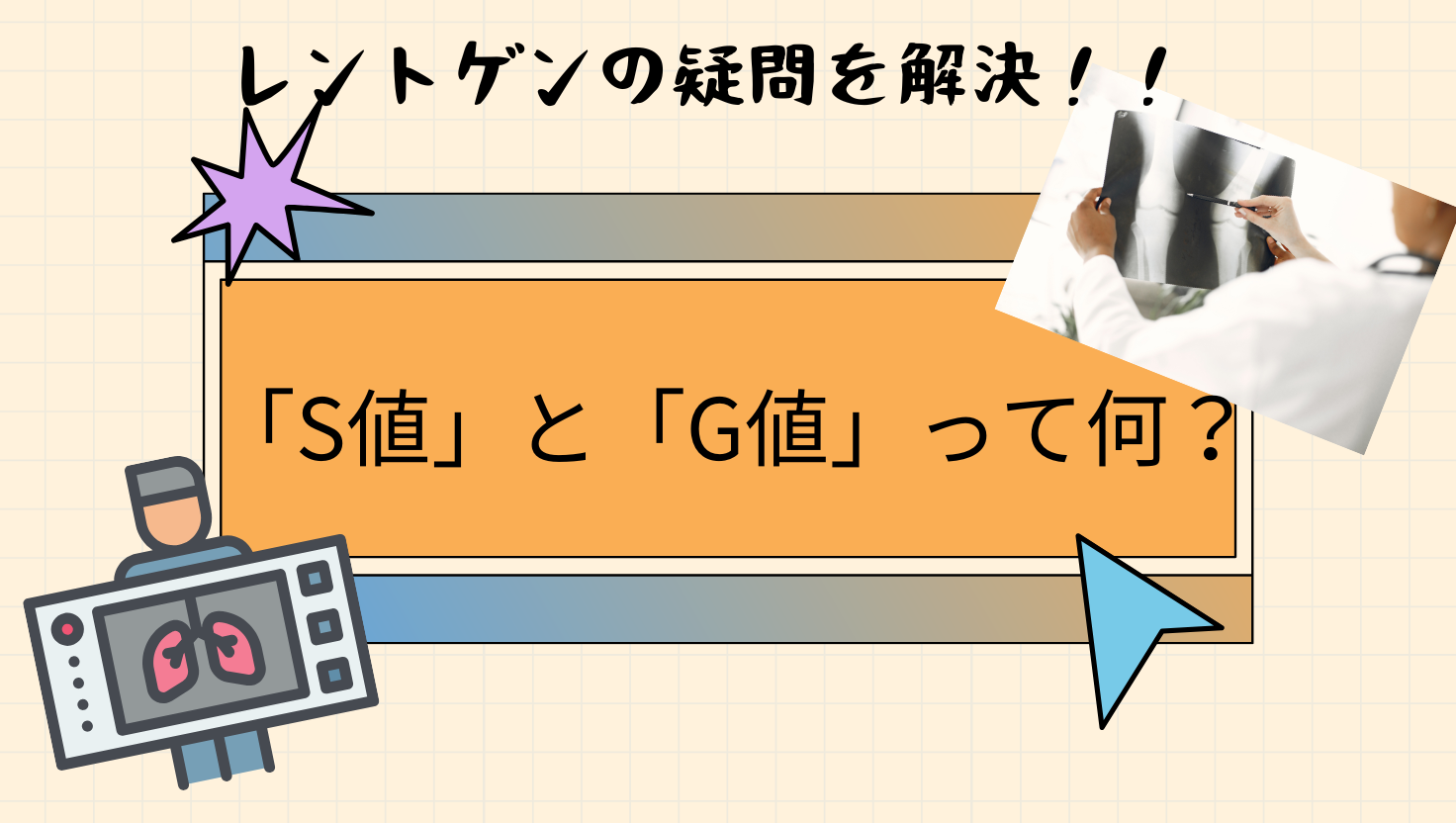【放射線技師が知っておきたい!】画像の質を高める2つの基本テクニック
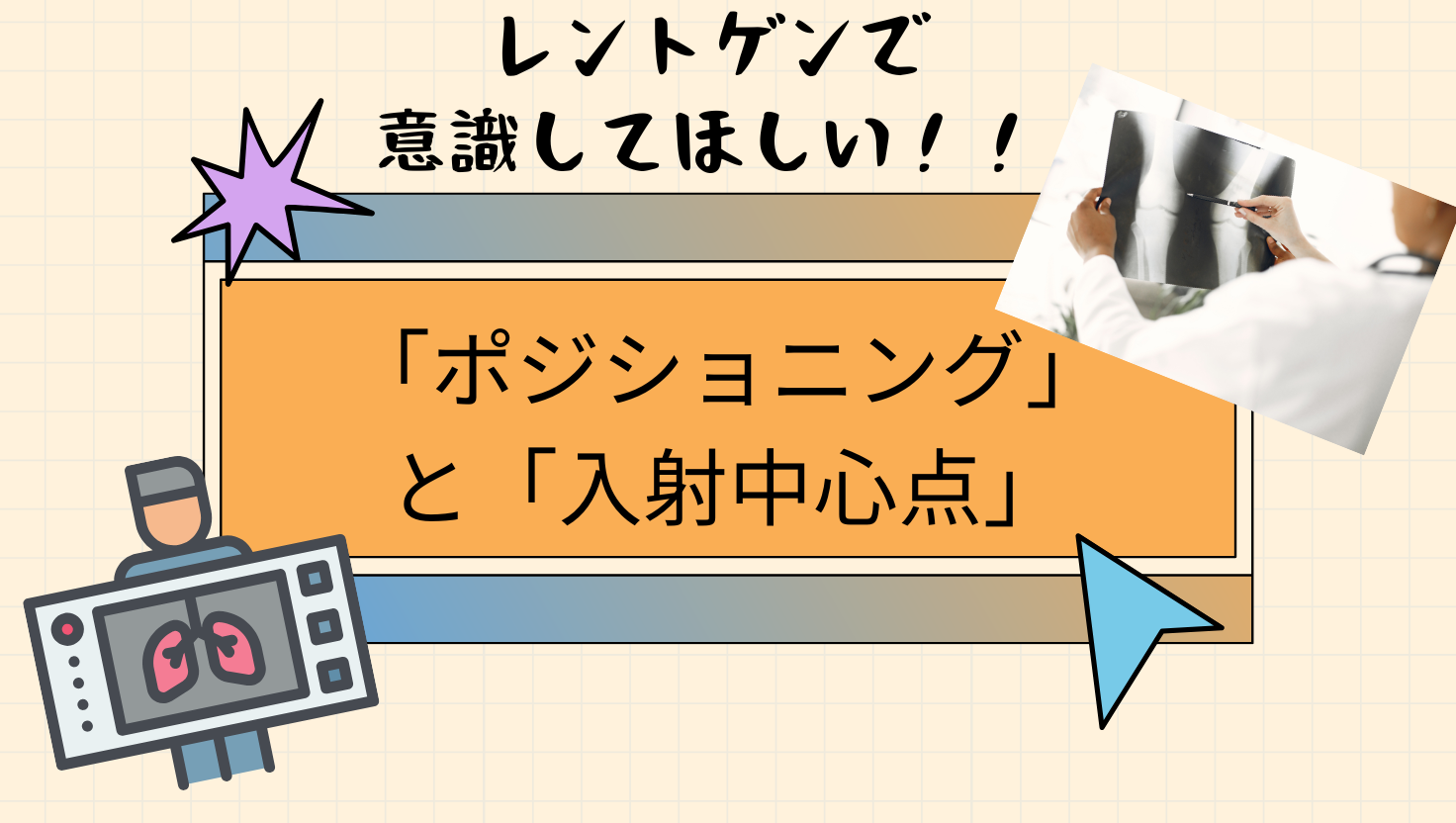
画像の質は“撮影条件”だけじゃ決まらない

レントゲン撮影はシンプルに見えて、結構奥が深いものです。撮影を続ける中で何気なくそのことに気づく放射線技師の方も多いのではないでしょうか?
撮影条件については、AECである程度最適な線量に調整されます。患者の体格によっては、手動で微調整を行うことでより最適な画像の撮影に近づけることが多いです。
そんな方に朗報です!レントゲン撮影をさらに上達させるポイントが撮影条件以外にもまだあります!
今回の記事では、撮影条件以外に、レントゲン撮影において意識してほしい重要な要素を2つ紹介します。
この記事を読めば、レントゲン撮影が上達して、より読影&所見の発見がしやすい画像を撮影できるようになるでしょう!!

- 「きんちゃん」20代診療放射線技師
- 放射線技師歴5年目(2025年4月30日現在)
- 大学病院、総合病院、中小規模病院(脳神経メイン、循環器メイン)経験
- 2回の転職で、XP、CT、MRI、骨密度測定、透視、アンギオ、放射線治療を経験
撮影条件は良いのに、いまひとつな画像。そんな時は、、、

撮影条件の調整は、皆様が務めている職場で先輩から教わっている方がほとんどでしょう。
+αで詳しく知っておきたい、という方はこちらの記事も併せてご覧ください。部位別の撮影条件一覧と、パラメータの詳細、画像への影響をまとめています。
![[新人技師必見!]レントゲンの撮影条件&mAs値一覧と最適な線量の考え方](https://kinchan-ayumi.com/wp-content/uploads/2025/05/1a4a8828f834bd0423a3398764f53d95.png)

なんかイマイチな画像になってしまうんだよな〜
という方に向けて、撮影条件以外に、レントゲン撮影において意識してほしい重要な要素を2つ紹介します。
それは、この2つです!
いやいやちゃんとやってるよ(笑)という言葉はいったん飲み込んでもらって、もう一度思い返してみてください。
- 画像の中心に撮影目的部位はあるか?
- 姿勢保持が困難な患者ではないか?
- ポジショニング固定具がアンバランスではないか?
いまいちかも、、、と思った方は一緒にポジショニングと入射中心点の重要性をおさらいしましょう!!
ポジショニングの再確認

まずはポジショニングの確認からです。皆様ご存じの通り、ポジショニングは、レントゲン撮影の基本でありながら、忙しさの中でつい流れ作業になってしまうこともある工程です。
整形領域は特にポジショニングの重要性が高いので、いかに関節をそろえて抜けるか?が大事になってきますね!
レントゲンにおける撮影部位を大きく2つに分けて、お話ししていきます。
- 流れ作業になりがちな部位(胸写、腹写など)
- ついつい時間がかかってしまう部位(整形領域など)
流れ作業になりがちな部位(胸写、腹写など)

流れ作業になりがちな部位の代表例として、胸写、腹写を挙げました。新人がまずできるようになる検査として、慣れからポジショニングが雑になってしまいがちではないでしょうか、、、?
こういった検査で油断すると見落としがちなポイントはこちらです。
回転率も意識しないといけない病院では、ついつい見落としてしまいがちですよね~
胸写の場合を例にして、具体的なケースをまとめました。改めて、確認していきましょう!
指示した内容が理解されていない

高齢者や、認知の入った方に多い印象ですが、それ以外でも意外と当てはまる人が大勢います。
- 腕を前に出していない
- 検出器と胸に隙間がある(胸をピタッとくっつけていない)
- 肩甲骨を前に出せていない(肺野に重なっている)
- ボタンやチャック、アクセサリーが撮影範囲に入っている
- 息を十分に吸ってない、息を止めていない
経験した方も多いのではないでしょうか?こちらはすべて、きんちゃんが実際に経験した内容でもあります。
1日の撮影件数が100を超える施設では、必然的にこのような患者も増えがちです。いずれも撮影する上で大切なポジショニングであることは放射線技師の方ならご存じのはず。一つずつ、もう一度丁寧に確認していきましょう。
再撮影も無駄な被ばく&効率が落ちることに繋がってしまい、誰も得しないですからね、、、(笑)
ちなみに、胸写、そして腹写の確認がしたい方はこちらの記事をどうぞ!定期的に学び直してマンネリ化を防ぎましょう!


立っている(あるいは座っている)場所がずれている
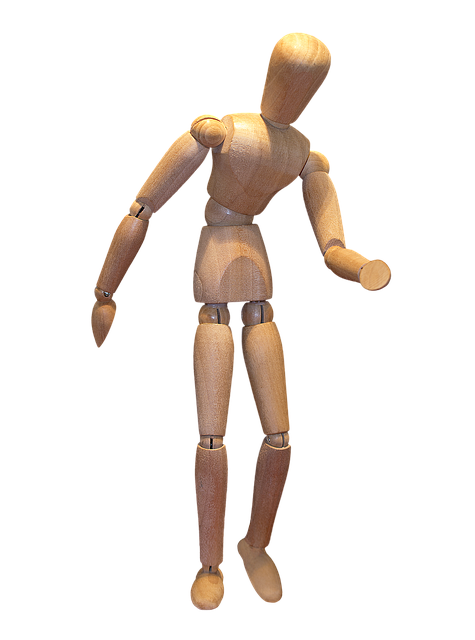
入射中心点にも少し関係してくる内容です。患者本人がしんどい姿勢でポジショニングしたら、ついつい力を抜いて立ち位置がずれていた、なんてことが前にありました。
脳神経外科メインの病院で働いていた時の話です。片足が不自由で杖歩行の方でした。
ポジショニングが完了してから実際に撮影を行うまでの間で動いてしまったがゆえに、想定していた場所からずれてしまった、と考えました。
これによるデメリットは、場合によっては再撮影になること、入射中心点がずれてしまうこと、の2点です。
車いす座位で撮影する場合にも同様のことが言えます。特に車いすの患者は、姿勢をまっすぐに座っていることが困難な場合が多いです。
撮影する直前に、いまいちどポジショニングが問題ないか確認してから曝射することを心がけてみると良いでしょう👍
入射中心点については、後半でお話ししますね。
身体がやや斜めになっている

胸をピタッとパネルに付けているつもりでも、微妙に体が斜めになっていることもあります。患者本人の姿勢保持が難しいため以外にも、無意識で斜めになっていた、なんてことも。
撮影直前に患者のポジショニングを確認して、必要に応じた調整をする必要がありますね。正面撮影なのに斜位を撮影するわけにはいかないですから(笑)
個人的な調整方法としてですが、きんちゃんは撮影直前に、患者の肩甲骨を前に押し出すようにしています。(肺野から肩甲骨を外すため)
この時に斜めになっていたらまっすぐ正面にポジショニングを補正できるので、ぜひ試してみてください!👍
ついつい時間がかかってしまう部位(整形領域など)

ついつい時間がかかってしまう部位の代表例として整形領域が挙げられます。関節をきれいに抜けるか、左右の骨をピタッと揃えられるか、で画像の良し悪しが変わってくるので、迷走して時間がかかってしまいがち、、、
同じような経験をした技師さんも多いのではないでしょうか?(きんちゃんの技術が未熟なせいもあるかもですが、、、)
時間がかかってしまいそうな部位の撮影では、こんな点に気を付けたいですね。
レントゲン室が一つしかない病院では、整形領域の撮影で詰まると一気に流れが滞ってしまいますよね(笑)
今回は膝の側面撮影を例に、具体的なケースをまとめてみました。
どう修正すれば良い画像になるか分かっていない

画像引用:https://imaging-diagnosis.com/view/4nHqNDvz
膝の側面撮影で重要なのは「内果と外果をきれいにそろえる」、ということは多くの技師がご存じのことでしょう。では実際に撮影した1枚目の画像を見て、どう修正すれば「内果と外果が揃った画像」にできるか分かりますか?
知識不足、技術不足が原因で検査を進めるスピードが落ちてしまう、ということです。
こうなってしまっては、一人で対処しきるには時間がかかり過ぎてしまいます。患者本人もしんどくなってしまうので、速やかに先輩などほかのスタッフに助けを求めましょう。
そして、次に撮影するときはどう修正すれば良いのか?という疑問が起こらないようにアドバイスや着目ポイントも教わると、あなた自身の成長に繋がりますよ👍
姿勢保持ができていない

膝の側面撮影では、健常な人でもなかなか保持の難しい姿勢になります。それが動きの悪い患者や高齢者であれば、姿勢保持の難易度は一気に上がることは想像しやすいでしょう。
完ぺきに合わせていざ撮影!となっても、ポジショニング完了→撮影ボタンを押す、までラグがあればあるほど、患者の姿勢が崩れやすいです。
せっかく良いポジショニングができてもこれでは意味がなくなってしまいますね。
対応策は2つあります。
- 自分は姿勢保持に徹して、他の技師に撮影ボタンを押してもらう。
- 撮影ボタンを持って姿勢保持を行い、ここだと思った位置で撮影ボタンを押す。
下手に時間をかけるくらいなら最初からこうした方が早く終わります。もちろん、被ばくを最小限にするために、プロテクタを着用するなどの放射線防護はしっかり行いましょう!
撤退ラインを把握しきれていない

何度位置調整をしても、内果と外果がきれいにそろわない患者はそこそこいます。体感ですが、変形性膝関節症に多い傾向です。
撮影回数、撮影時間が増えるほど、患者への被ばくも増加します。撮影する技師も大変ですが、姿勢保持をしている患者本人もしんどいです。
あまりに合わないときは、素直に先輩に助けを求めましょう。案外あっさり解決することもありますし、逆に今まで撮影した画像で良い、という判断になることもあります。
自分の中で、「〇回撮影して合わなかったら撤退して、先輩に助けを求めよう!」と事前に決めておくことをおすすめします。
ちなみにきんちゃんの撤退ラインは、3回撮影しても良い画像が取れる見込みがなかったら、です!
入射中心点の再確認

続けて、入射中心点の再確認です。ポジショニングと同じくらい、良い画像を撮影するために重要な要素だときんちゃんは考えます。
今まで3か所の病院を経験していろいろの放射線技師に会ってきましたが、中にはこのような方がいました。

撮影範囲に入っていればいいよ
ケースバイケースだとは思います。患者の保持が困難(意思疎通不可で暴れる、など)の場合はやむを得ないでしょう。
ですが、きちんと意思疎通ができて撮影ポジショニングの姿勢保持が可能な患者にまでそのような考えで撮影してしまうのは、ナンセンスではないかと思います。
入射中心点を重要視する理由は2つあります。
- 画像評価がいまいち
- 再現性が悪くなる
ではなぜ入射中心点がそこまで重要なのか、詳しく見ていきましょう。
画像評価がいまいち

レントゲン撮影では、被写体に対して垂直にX線が入射する必要があります。斜めに入射すると、過大評価や過小評価になってしまうからです。
また、せっかくきれいにポジショニングしても、斜めから入射しては関節が抜けていない微妙な画像しか撮れません。
微妙な画像では、読影医も困りますし患者のためにもならないですよね。
左右同時に撮るのは、あまりイケていない

画像引用:https://www.kumamoto-rt.or.jp/publics/xsatsuei/
上記画像のように、左右比較目的で出されたオーダーを圧縮して撮影する施設が多いのではないでしょうか?
技師側からしたら効率が良いですし、患者側としても一度の撮影で2部位まとめて撮影してもらえるなら楽でしょう。
しかし、入射中心点について考えるならこのやり方はイケていないときんちゃんは感じます。
左右それぞれの手部を評価したいのに、両方とも斜めにX線が入射したことで撮影された画像です。これでは正しい評価ができるとは言えない、そう思いませんか?(きんちゃんの主観が入っています)
オーダーも、「右手 手部 正面」と「左手 手部 正面」で分かれて出ていたはずです。
今一度、入射中心点も考慮しながら撮影することで、画像評価、読影がしやすい画像を撮影出来るでしょう。
再現性が悪くなる

入射中心点を意識することは、再現性を高く保つことにもつながります。レントゲン撮影での撮影の目的の一つに、経過観察(follow-up)があります。
オーダーコメントや検査目的にその旨の記載を見たことがあると思います。
経時的な変化で、良くなっているのか?悪くなっているのか?を判断して方針を決めるので、毎回撮影する画像は同じようなものであることが望ましいです。
レントゲン撮影の教科書などで記されている入射中心点にX線管球を合わせて毎回撮影をしましょう。それが、再現性を高く保つことに繋がります。👍
まとめ:基本の確認が、質の高い画像を作る

レントゲン撮影で“なんとなく納得できない画像”が撮れてしまう原因は、意外と基本的な部分にあるものです。
撮影条件を意識することはもちろん大事ですが、今回の記事でお話しした「ポジショニング」と「入射中心点」も忘れてはいけません。
この2つを意識するだけで、同じ条件でも納得のいく画像が得られることがあります。
一つひとつの撮影を“なんとなく”で終わらせず、「これで良いのか?」と自問自答することが、放射線技師としてのレベルアップに繋がります。ぜひ明日の撮影から、意識してみてください!
![[2回利用経験あり]怪しい?しつこい?放射線技師人材バンクの評判や気づいたことまとめ](https://kinchan-ayumi.com/wp-content/uploads/2025/07/60db68b212d3da0848a7361614a6e975-320x180.png)
ではまた