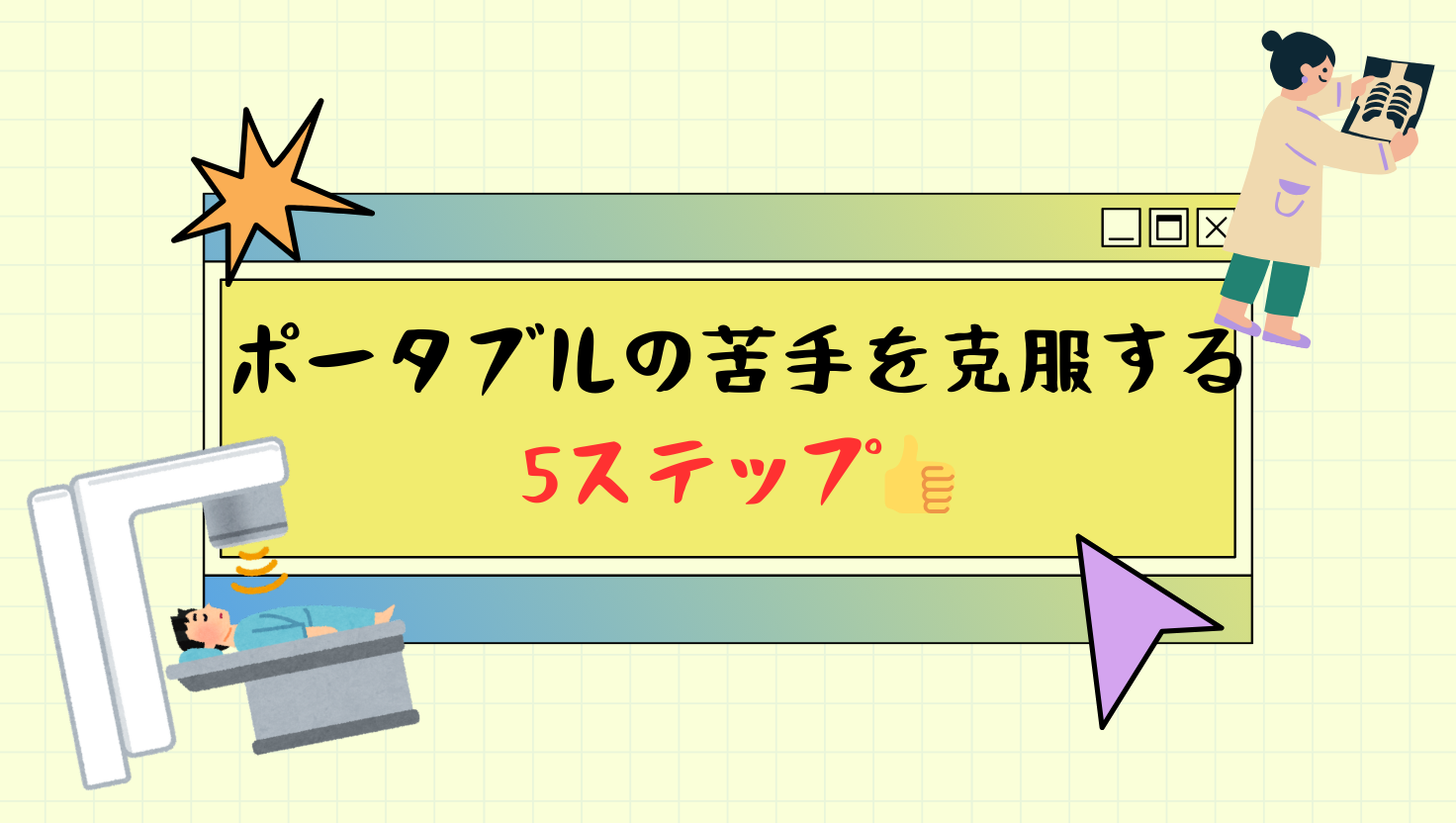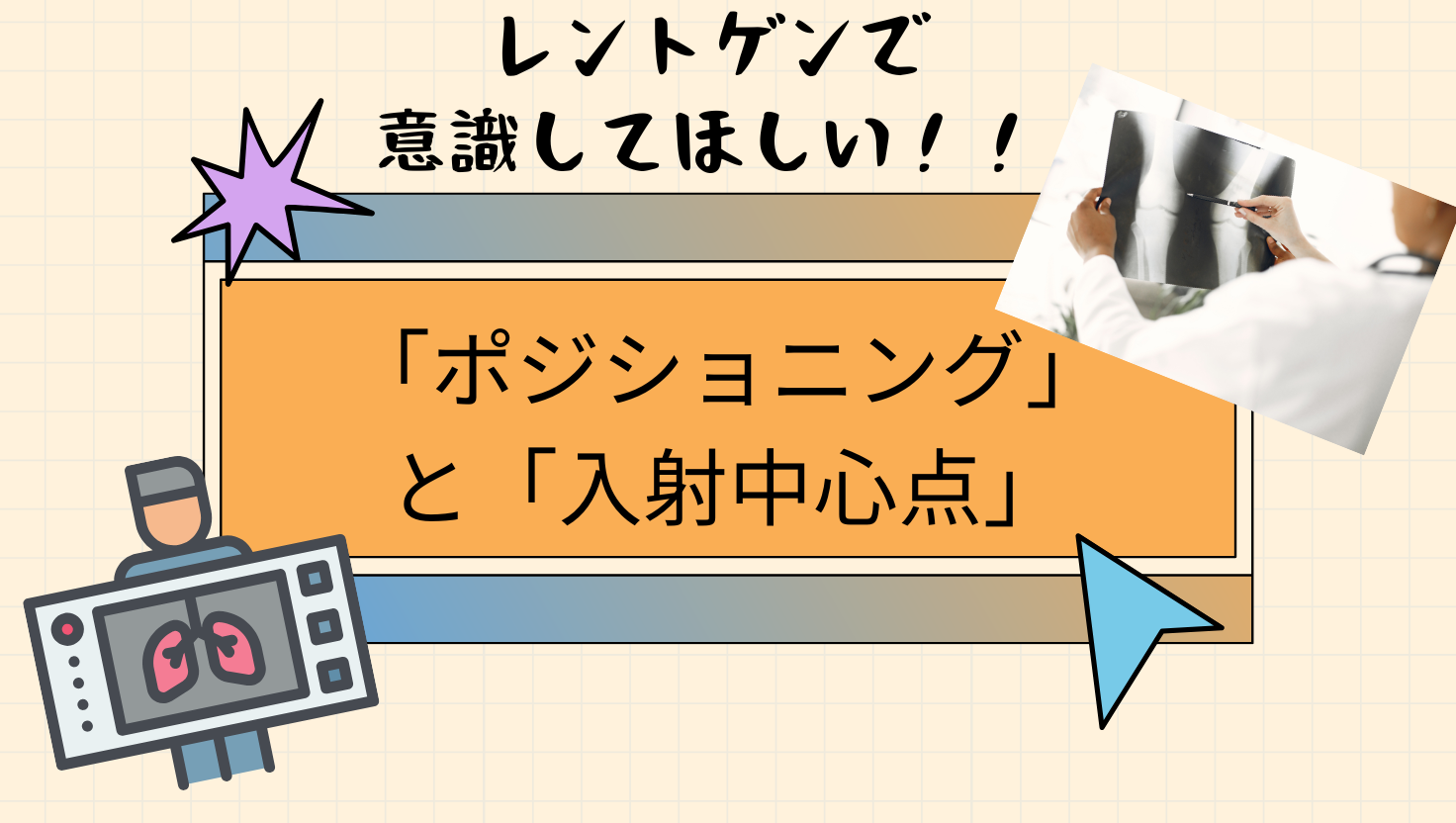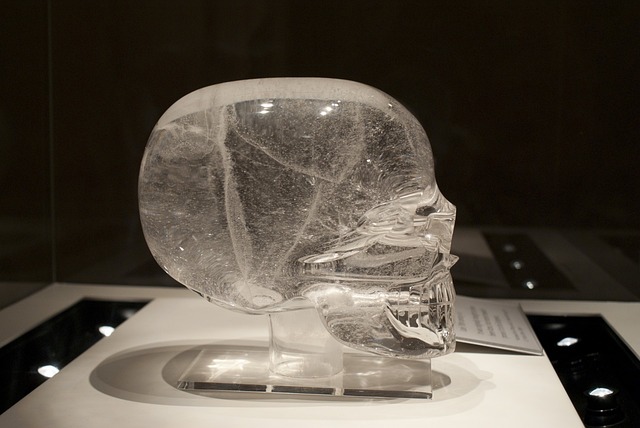[新人技師必見!]レントゲンの撮影条件&mAs値一覧と最適な線量の考え方
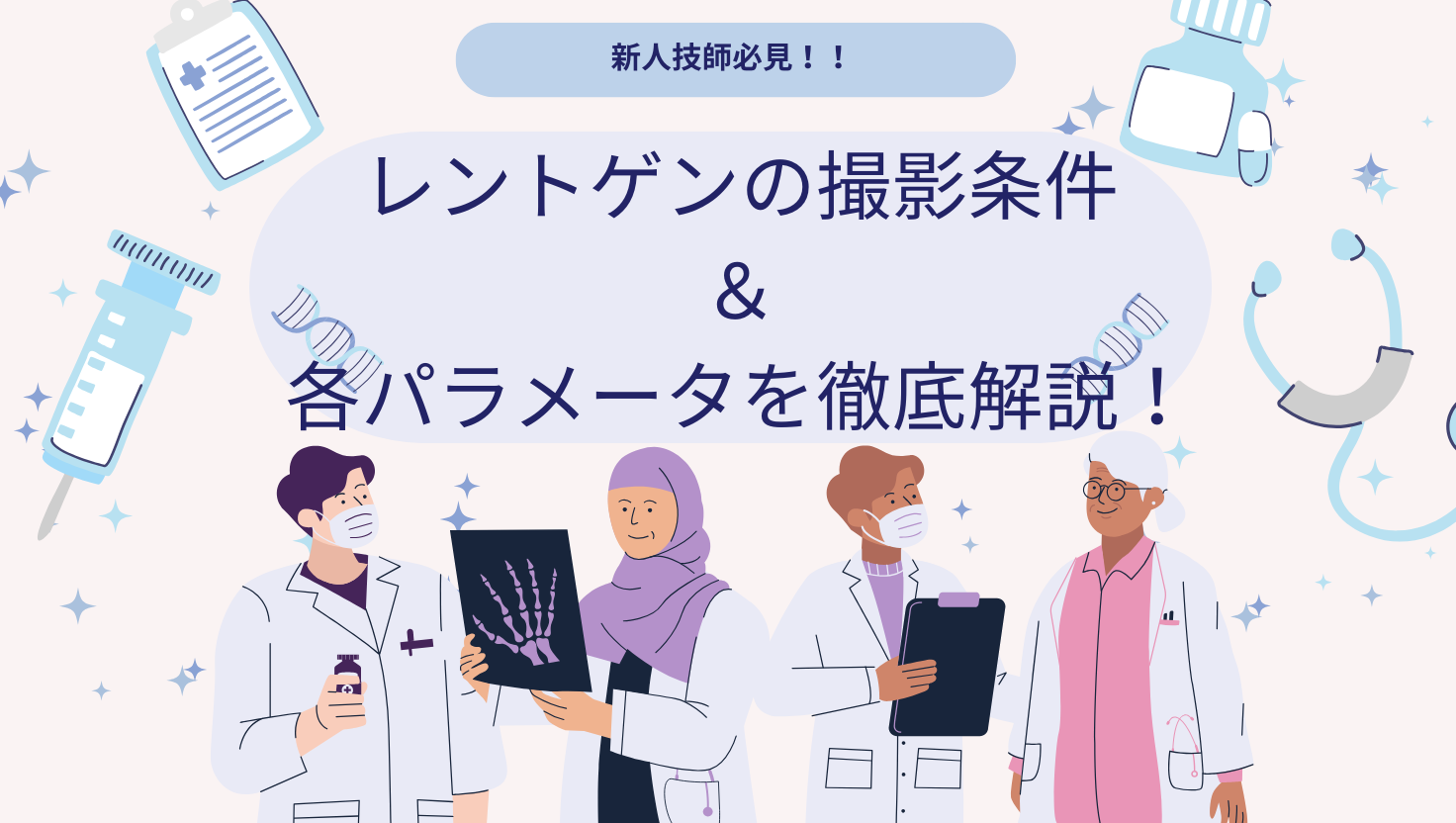
レントゲンは日常診療の基盤。
目的は「診断可能な画質を最適な線量で」——この記事はそのための“順番と目安”を現場向けにまとめました。

AECに任せれば写るけど、外したときに何をどれだけ動かすかが分からない、、、
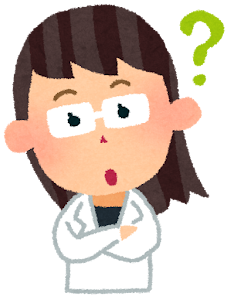
SIDやグリッドが絡むと、kVとmAsのさじ加減に自信がない
そのモヤモヤ、よく分かります。私も新人のころは同じでした。
この記事では、放射線技師としての現場経験をもとに、撮影条件の基本と撮影部位ごとの目安について、分かりやすく整理しています。
- 撮影部位別の撮影条件一覧
- 線量がイマイチな時の調整方法
- EI/S値・DIの意味と調整幅
新人技師の方にまず知ってほしいパラメータは以下の通りです!
- 管電圧(kV)
- 管電流(mA)
- 撮影時間(s)
- mAs値(mAs)
- 撮影距離(cm)
- グリッドの有無
そして撮影後は、EI/S値・DIで必ず“答え合わせ”をし、次回の撮影条件調整の際に活かせるようにしましょう!
撮影条件の設定に迷ったときは、以下の目安も役立ててください!
- kV±5〜10(※15%ルール:kVを約15%上げると受光量約2倍→mAsは半分で同等露光)
- 体厚±2cm ⇒ mAs±15〜25%
- SID補正は逆二乗(例:100→150cm=×2.25)
- グリッド係数:5:1→約2倍/8:1→約3〜4倍/12:1→約4〜5倍
- 動き対策:**時間を短く(s↓)→mA↑**でmAsを維持

- 「きんちゃん」20代診療放射線技師
- 放射線技師歴5年目(2025年4月30日現在)
- 大学病院、総合病院、中小規模病院(脳神経メイン、循環器メイン)経験
- 2回の転職で、XP、CT、MRI、骨密度測定、透視、アンギオ、放射線治療を経験
よくある撮影現場のつまずき

レントゲン撮影をするときに重要なのはポジショニングと撮影条件です。AEC(自動露出制御)で撮影条件は勝手に最適化されますが、たまに手動で線量をいじっている先輩を見ませんか?
この記事では以下の悩みに対する疑問を解決できるような話をまとめています。
撮影条件を間違えると、再撮影や診断ミスにつながり、患者さんの被曝リスクも増えてしまいます。
その不安を少しでも解消できるよう、部位別の標準撮影条件と、各パラメータの意味・使い方をまとめました。
最後まで読むことで、レントゲン撮影に対する不安を減らし、自信をもって撮影ができるようになりますよ!
EI / S値・DIとは?(撮影後の“答え合わせ”指標)
上記で述べたEI / S値・DIについての説明からまず行います。
- EI(Exposure Index)
検出器に入った入射空気カーマ(受光量)の“目安”を表す数値。基本は受光量に比例(値が大きい=多く当たった)。装置やメーカーで表示スケールは異なる(IEC準拠EI、CarestreamのEIなど)が、意味は「受光量の大小」。 - S値(Sensitivity Number)
主にCRで使われる指標。受光量に反比例(値が大きい=露光不足、値が小さい=過剰露光)。機種ごとに目標値が決まるので、施設の基準表を優先。 - DI(Deviation Index)
目標露光(装置に設定されたターゲットEI)からのズレを対数で表示したもの。
計算イメージ:DI = 10 × log10(実測EI / 目標EI)- DI=0 … 目標どおり
- +1 … 約**+26%**多い(過剰)
- −1 … 約**−21%**少ない(不足)
DIの目安(覚えやすい早見)
| DI | 露光量の比 |
|---|---|
| −3 | 約×0.50 |
| −2 | 約×0.63 |
| −1 | 約×0.79 |
| 0 | ×1.00 |
| +1 | 約×1.26 |
| +2 | 約×1.58 |
| +3 | 約×2.00 |
例:目標EI=400で実測EI=500なら、DI≒+1(約25%多い)→mAsを約20%下げるかkV−5などで調整。
EI / S値・DIの使い方(現場運用)
- 撮影後にEI/S値・DIを確認(DIは±1以内を目指す)。
- 不足(DI<−1):mAs+10〜30% or kV+5。
過剰(DI>+1):mAs−10〜30% or kV−5。 - 変更内容を自分の基準表にメモして更新。
EI / S値・DIの注意点(落とし穴)
- 患者線量そのものではない(受光量の指標)。
- コリメーション不良・義肢・造影剤・画像トリミングで指数が乱れる。
- メーカー/装置で表示名と目標レンジが異なる(施設の基準値を必ず確認)。
この3指標で“露光が適正だったか”を数値で振り返ると、再撮影率を下げつつ、最適な線量に素早く近づけられます。
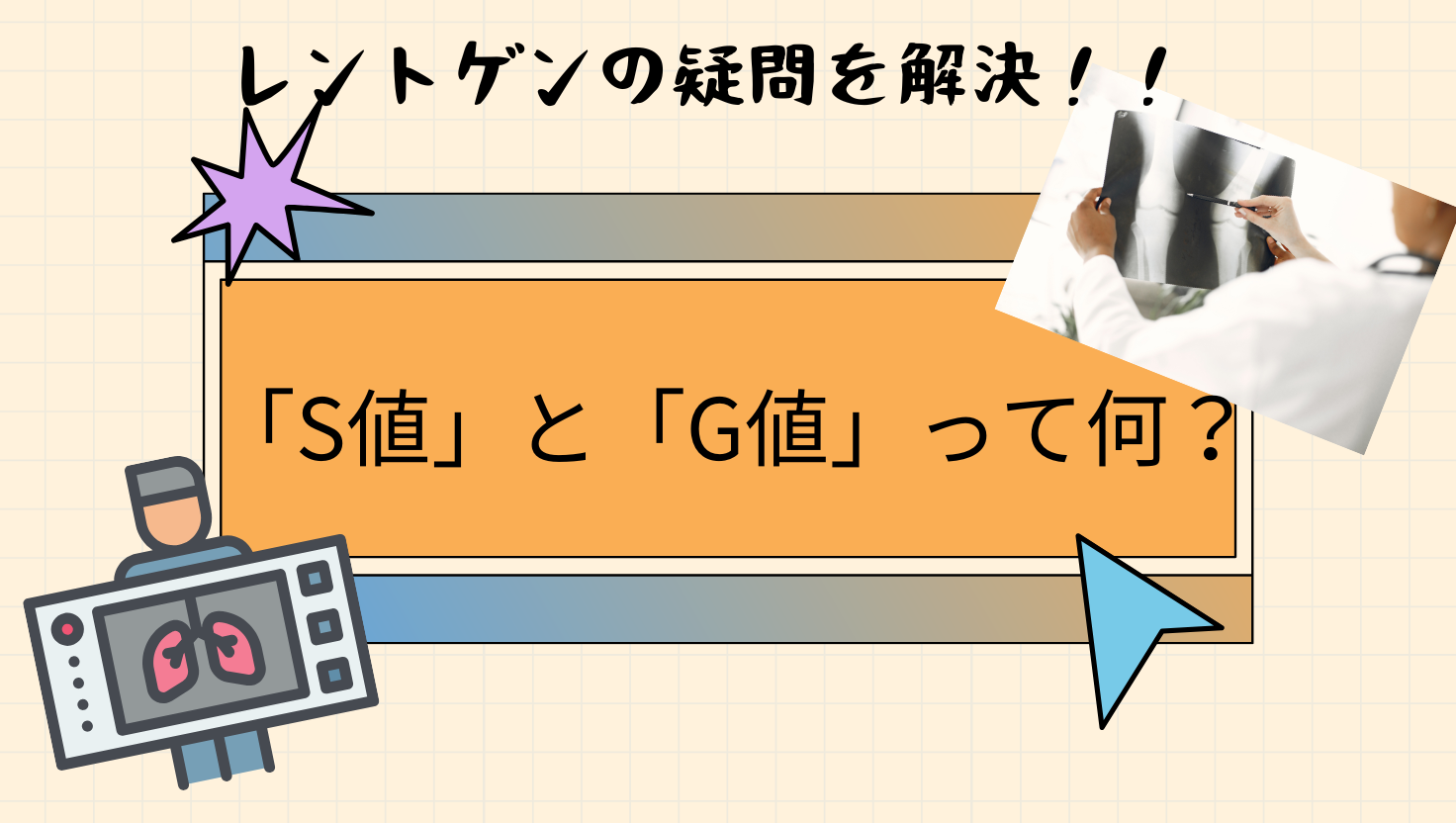
撮影部位別:参考条件一覧表

きんちゃんが撮影経験のある部位を中心に、部位ごとの撮影条件を表にまとめました!
病院ごとにそれぞれ若干異なるとは思いますが、おおむね妥当な数値になっているのではないでしょうか?
なお、当記事ではこちらの参考書からの数値を一部引用しています。
それでは、以下、撮影部位ごとの撮影条件になります!
まずは代表的な部位、撮影条件を5つご紹介します。
| 撮影部位 | 体位 | 管電圧 (kV) | 管電流 (mA) | 撮影時間 (ms) | mAs | 撮影距離(SID, cm) | グリッド |
| 胸部 正面(PA) | 立位 | 120 | 100 | 32 | 3.2 | 200 | - |
| 腹部 正面(AP) | 仰臥位 | 70 | 200 | 100 | 20 | 100 | - |
| 頭部 正面(AP) | 仰臥位 | 70 | 200 | 100 | 20 | 100 | ○ |
| 骨盤部 正面(AP) | 仰臥位 | 70 | 200 | 120 | 24 | 100 | ○ |
| 大腿骨 正面(AP) | 仰臥位 | 70 | 200 | 100 | 20 | 100 | ○ |
※1:10–20 ms=0.01–0.02 s 目安
※2:○=使用、−=非使用
使い方(画像がイマイチな時の動かし方・超要約)
- 厚い/抜けない:kV+5〜10 か mAs+15〜25%
- 動く(ブレる):**時間↓(s短縮)→ mA↑**でmAs維持
- SID変更:逆二乗で補正(例:100→150 cm=×2.25)
- グリッド使用:受光量が減るのでmAsを約2〜5倍(5:1=約2倍、8:1=約3〜4倍、12:1=約4〜5倍)
- 撮影後はEI/S値・DIで“答え合わせ”→次回へ反映
この先で得られるもの
- 全身45行の部位別詳細表(kV/mA/ms/mAs/SID/グリッド)
- SID変更・グリッド使用・体厚差を織り込んだ補正済み早見表