【苦手克服!】ポータブル撮影が上手くなる5ステップ|新人技師のための実践マニュアル
きんちゃん
きんちゃんのラジエーションハウス
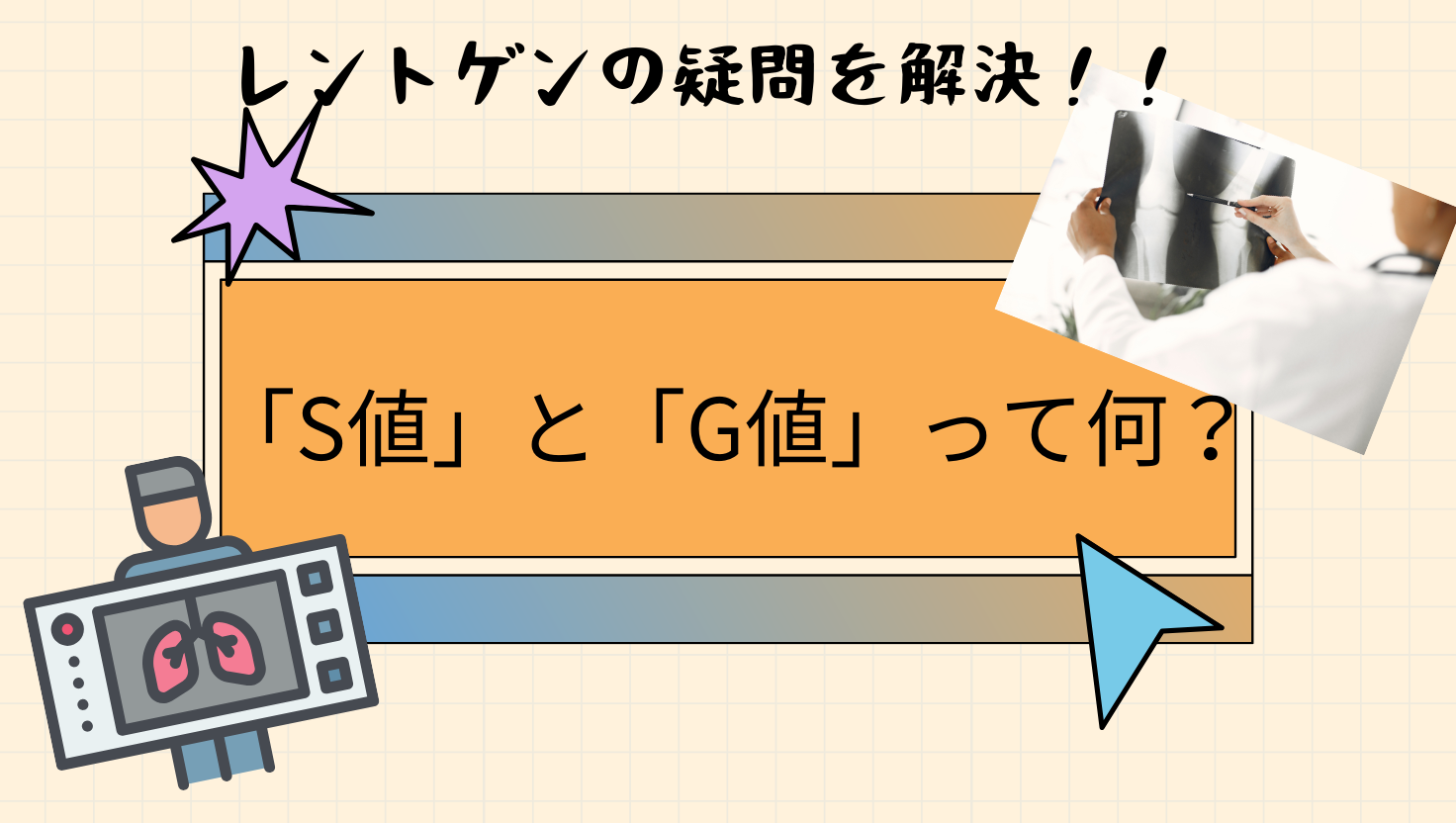

レントゲン撮影に日々明け暮れている放射線技師の皆さん、お疲れ様です!新人技師の方はぼちぼち業務にも慣れてきたのではないでしょうか?
特に最初に教わることの多いレントゲン撮影は、ほぼ1人で回せるようになっていることでしょう。ですが、撮影をするだけでは技師免許さえあれば誰でも出来てしまうのもまた事実。
より知識を身に付けることで、職場の先輩のように優秀な放射線技師になるのです。自己成長を目指すのであれば知っていて損しない、そんなテーマとして「S値とG値」を本記事でまとめてみました。
新人技師はもちろん、それ以外の技師の方にも役立つ内容になっていますので、ぜひ最後までご覧ください!

レントゲン撮影をすると、画像の右上にS値:○○、G値:○○と表示されますよね。これらは画像の見た目を変えるときに調整する数値であり、PACSに送信する前に見やすい画像にすることが我々放射線技師の専門業務でもあります。
でもここで悩んでいる方が多いのは周知の事実!
PACS送信前に、先輩技師がピピっと画像の濃淡を調整していますが、どのような意図があってその色にしたのかを知らない方がほとんどでしょう。
逆に先輩技師側も、正直何となくで色合わせをしている方も多いのではないでしょうか、、、?(ブーメラン発言😅)
そんな皆様の悩みを少しでも解消できるようになるべくかみ砕いてお話しさせていただきます!

S値とG値は結局何なのでしょうか?ズバリこのことです。